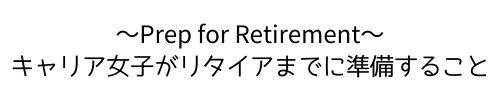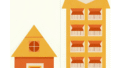最近、早期退職制度を実施するという企業のニュースを目にすることが多かった気がします。
65歳年金受給が標準型とされる一方で、65歳を待たずにリタイアするセカンドライフの選択肢もポピュラーとなりつつあるのかなと私の周りを見ていても思います。
一般的には、年金額が目減りする60歳からの繰り上げ受給は、受取総額は目減りすると言われていますが、65歳まで働きたくない私。。
60歳受給のメリットが本当にないのか、探してみたいと思います。
損益分岐点は77歳
60歳から繰り上げ受給する場合、65歳の標準型から24%減額され、これが一生涯続きます。
また、いちど繰り上げ受給するとこれを変更することはできません。つまり一生76%の年金しかもらえません。
一般的に77歳が損益分岐点と言われており、77歳よりも長生きする場合は、65歳受給の方が受取総額は多くなり、長生きすればするほど、メリットは大きくなるということになります。
平均寿命が80歳を超えていますから、やはり一般的には65歳受給の方がおすすめなのでしょう。
ねんきんネットでシミュレーションできます https://www.nenkin.go.jp/n_net/
制度リスクやインフレリスクに強いのは?
一方で、日本の年金制度が盤石とは言えないことは周知の事実。制度変更が将来起こる可能性は大いにありますし、インフレリスクも外せません。
こうした社会変動リスクに耐性があるのはどちらでしょうか?
早めに確定した方がリスクヘッジできるのではないかと思ったのですが、必ずしもそうとも言えないようです。
制度変更リスク
-
現行の年金制度(国民年金・厚生年金)は「65歳支給」を標準として財政計算されている。
-
将来的に財政が厳しくなった場合、まず見直されるのは「繰上げ・繰下げの率」や「受給開始年齢」などのオプション部分。
-
つまり、「繰上げ受給者」が受ける減額率の見直しや、制度の再計算の影響を受けやすい。
一方で、年金財政は、現役世代の保険料で支える賦課方式。少子高齢化が進むと、現役世代の負担が増え、年金財政は厳しくなります。
その場合、政府が取りうる政策は:
-
受給開始年齢の引き上げ(例:65→68歳)
-
給付水準の抑制
-
高所得者への給付削減 など。
このうち、「すでに受給を始めている人」の年金を減額することは法的・政治的に難しいため、まだ受給を始める前の人ほと、制度改定の影響を受けやすいですね、やはり。
インフレリスク
日本では、年金は「物価スライド制+マクロ経済スライド」で調整されています。
インフレ・物価上昇時は、
-
現役世代の賃金が上がる一方で、年金の伸びは抑えられる傾向。
-
早く年金をもらい始めた人(繰上げ受給者)は、低い水準で固定されるため、物価上昇に追いつきにくく。
つまり、繰上げ受給は「インフレに弱い」
逆に、65歳受給であれば、
-
受給開始時点の年金額はその時点の物価に応じて調整済み。
-
将来インフレが進んでいれば、より高い初期年金額からスタートできる可能性があります。
制度変更は、改善よりも改悪の可能性の方が高いと思うので、60歳受給で早めに確定した方が影響を受けなくてすみますが、たしかにインフレへの対応はできないですね。
一長一短というところでしょうか。
年金受給と資産運用を組み合わせて考えてみる
65歳まで働くことが前提の年金制度、定年退職することが難しい。
年金受給を前倒しするか、資産切り崩しを前倒しするか、どちらしかありません。年金をもらう代わりに、資産運用した方が、もしかしたら有利なのかもしれません。
前提条件:
- 年金65歳受給:25万円/月
- 年金60歳繰り上げ受給:19万円/月
- 1ヶ月の生活費:30万円/月
- 60歳時点の株式資産:5,000万円
- 運用利回り:年利3%
上記条件で、年金と生活費不足分を運用しながら資産切り崩した場合、損益分岐点の77歳時点での資産はどうなっているでしょうか。
77歳時点での資産残高:
- 60歳受給:約3,700万円
- 65歳受給:約3,500万円
結論は、「大きく変わらない」でした。
逆に、77歳を過ぎると、資産残高の点でも65歳受給がどんどん有利になっていきます。
うーん、、色々な見方をしてみましたが、経済計算上はやはり65歳受給に軍配があがります。
ただ、60歳から64歳までの5年間は貴重です。現役時代と同じレベルのフィジカルがあり、新しいことや難易度の高いことにチャレンジできる人生で最後の5年ではないでしょうか。
この貴重な5年を会社という組織に縛られ続けることのデメリットは、経済メリットを上回るかもしれません。
大事なことは、60歳になってからオロオロして、のちのち後悔するような拙速な選択をしないよう、50代の今から考えておくことです。
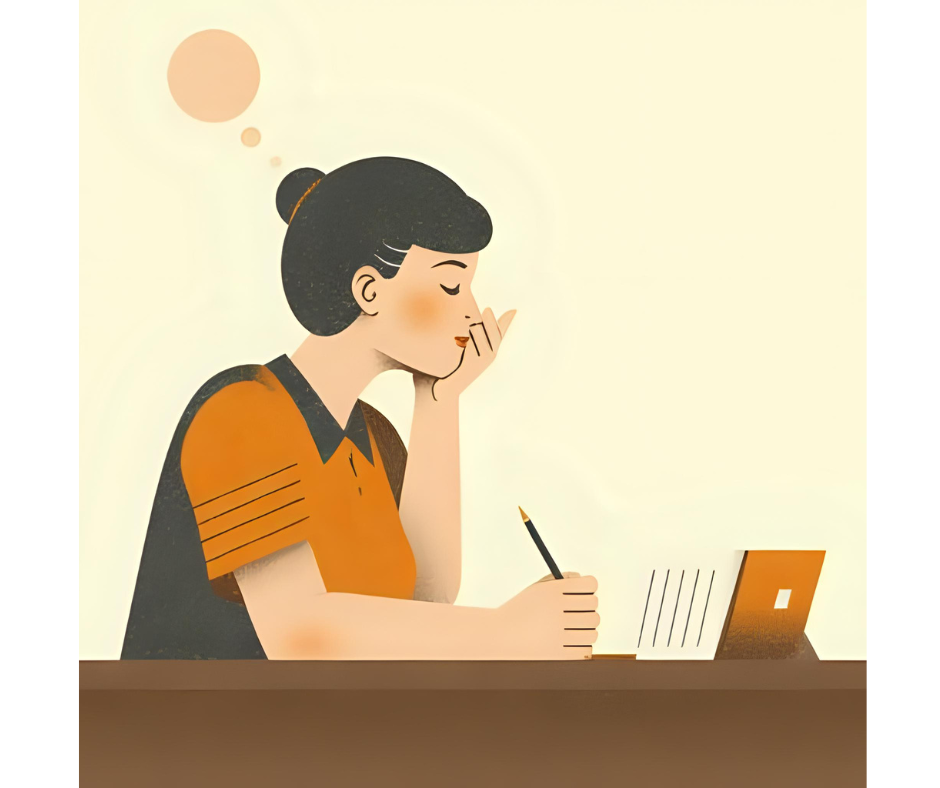
インデックス投資を4%ルールで切り崩すのと、高配当株投資(楽天SCHD)の配当金、同じ元手資金だったらどちらが手取り多いんだろう?