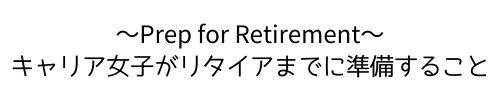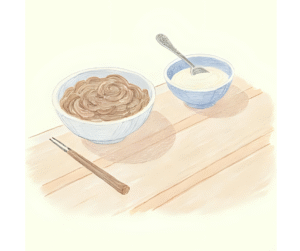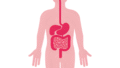あるとき、左手の人差し指の第2関節に鈍い痛みがあり、どこかで突き指したかなと思っていたら、他の指にも広がっていき、朝起きたら手がこわばるようになりました。
もしかして、リウマチの初期症状かもと思い、リウマチ専門医に行って検査してもらいました。幸いなことに結果は陰性。
しかし、とすると、この痛みは・・?もしかして、これが更年期症状というやつなの??
今まで、更年期症状なるものを意識したことがなかったのですが、年齢を考えれば、たしかになにかしら症状が出てもおかしくはありません。
更年期症状とは、どのような症状を言うのか?
更年期とは、閉経を挟んだ前後5年間くらいの事を更年期と呼ぶのだそう。(ずっと続くわけではないのですね)
この時期、卵巣の機能が低下し、エストロゲンが急激に減少することで生じる様々な心身の変化を更年期症状というのだそう。
| 区分 | 症状 | 原因・特徴 |
|---|
| ① 血管運動神経系の症状 | ほてり、のぼせ、発汗(特に顔・首)急な寒気 | エストロゲン低下により自律神経のバランスが乱れる |
| ② 精神・神経系の症状 | イライラ、気分の落ち込み 不眠、不安感、集中力低下 |
ホルモン変化+自律神経の乱れ+心理的ストレス |
| ③ 運動器系の症状 | 関節痛、肩こり、手足のこわばり | エストロゲンの減少で関節や筋肉の柔軟性が低下 |
| ④ 皮膚・粘膜系の症状 | 肌の乾燥、かゆみ | エストロゲン低下で粘膜や皮膚の水分保持力が低下 |
| ⑤ 泌尿器系の症状 | 頻尿、尿もれ、残尿感 | 骨盤底筋や尿道・膀胱粘膜の萎縮による |
| ⑥ その他 | 動悸、息切れ、めまい、頭痛、疲れやすさ | 自律神経失調による体調不良 |
更年期症状に大豆イソフラボンは効果的なのか?
イソフラボンは、女性ホルモンであるエストロゲンと似た作用を持つため、女性ホルモンの減少を補うことができるとよくいわれています。
イソフラボンの効果は、どこまで科学的に証明されているのでしょうか。
- 更年期の火照り・のぼせ:比較的多数の臨床データあり。
- 骨密度の維持:一部研究で有効性、継続摂取が必要。
- 関節痛・こわばり:根拠は限定的。閉経期の不快症状の一部に軽減症例あり。
- 乳がん予防:疫学的には関連あるも確定的ではない。
大豆イソフラボンは、「女性ホルモン低下による不調をやわらげるサポート成分」として一定の科学的裏付けがあるようですが、あくまで補助的なものと考えた方が良さそうです。
ゲニステインとエクオール
どちらも大豆イソフラボンに関係する成分です。
ゲニステイン(Genistein)
特徴:
- 大豆イソフラボンの主要成分のひとつ。
- 食品中にはそのまま含まれており、体内で直接働くタイプ。
- 弱いエストロゲン様作用と抗酸化作用を持ちます。
期待される作用:
- 骨の代謝バランスを整え、骨密度低下を抑える
- 血管を保護し、動脈硬化予防に役立つ可能性
- 抗酸化・抗炎症作用で肌や関節の老化予防にも関与
エクオール(Equol)
特徴
- 大豆イソフラボンの一種「ダイゼイン(Daidzein)」が、腸内細菌によって代謝されて生まれる成分。
- つまり、食べてすぐ摂れるのではなく、腸内環境によって作れる人・作れない人がいます。
(日本人女性では約50%が「エクオールを作れる体質」)
エクオールの働き
- エストロゲン作用が非常に強い(イソフラボンの約10倍)
- 特に更年期以降の女性で不足する女性ホルモンの代替的役割を果たす
- 主な効果
- ホットフラッシュ・イライラなどの更年期症状軽減
- 骨密度低下の抑制
- 関節痛・こわばりの軽減(エストロゲン低下に伴う炎症緩和)
- 肌弾力の維持(コラーゲン分解抑制)
日本人女性の半数がエクオールを作れる体質とのこと。確率50%・・微妙ですね。
作れる人と作れない人の違いは何なんでしょう?そして、作れない人も作れるようになることはあるのでしょうか?
エクオールを作れる人と作れない人
エクオールは、大豆イソフラボンの一種「ダイゼイン(daidzein)」を腸内の特定の菌(エクオール産生菌)が代謝して作ります。
つまり、「エクオールを作れる体質」というのは、この菌が腸内に“住みついているかどうか”で決まります。
日本人の約半数はもともとエクオールを作れませんが、研究では「食生活の改善でエクオール産生能が獲得・回復した」例も報告されています。
改善のポイント
① 大豆食品を継続的に摂る
エクオール菌は「大豆イソフラボンを餌にして生きる」ため、継続摂取が菌の定着を助けます。特に発酵大豆食品(納豆・味噌・テンペ)はおすすめ。
② 発酵食品や食物繊維で腸内環境を整える
腸内バランスが悪いと、エクオール菌が住み着けません。ヨーグルト、ぬか漬け、キムチ、納豆、食物繊維(野菜・海藻・きのこ類)を意識。
③ 動物性脂肪・精製糖質の摂りすぎを控える
悪玉菌が優勢になると、エクオール菌が活動しにくくなります。
④ プロバイオティクス・プレバイオティクスを利用
乳酸菌やオリゴ糖など、善玉菌のサポート食品も有効。
結局、腸環境を整えることが、心身を整えることにつながるんですね。
腸活を始めて、ヨーグルトメーカーで色々な種類のヨーグルトを作って食べるようにしているのですが、エクオール菌生成のためには、大豆の発酵食品が必要とのことなので、時々しか食べていなかった納豆をできるだけ毎日摂るようにしようと思います。
毎日、食べないといけないものがあって大変・・
とはいえ、腸内細菌が定着するには、数カ月はかかるとのこと。
今、自分の腸がエクオール菌を持っているかどうかわからないので、当面はサプリの力を借りて様子を見ることにします。