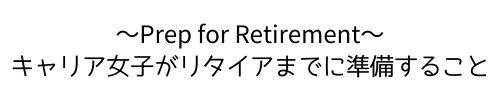NISAでS&P500やオルカンなどインデックス投資をしていますが、高配当株投資は投資初心者の自分には少しハードルが高いなと思っていました。VYM(米国高配当株式ETF)も考えたことはあるのですが、配当が出るとはいえ、株価の上がり方はスローなんだろうなと思うとなかなか手が出せませんでした。
一方で、S&P500など株価の値上りを期待する投資の場合、老後生活においては切り崩すことが前提になります。財産を切り崩すということが、いざそのタイミングになるとメンタル的に厳しいかもなとも思っていました。
そんな中、楽天SCHDが発売になりました。配当と株価値上りの両方が期待できる投資信託として、発売直後から人気となっています。
ケース1:配当再投資あり
配当再投資を行うと、複利効果によって投資元本が増えるため、将来の配当額が増える効果が期待できます。
- 目標元本計算:配当再投資ありで65歳時に月10万円の配当を得るためには、年間配当120万円 ÷ 0.035(配当利回り)=約3,430万円が必要
- 積立額シミュレーション:毎月の積立額を「年間5~7%のリターン」として計算します。
- **年間リターン5%**の場合:毎月約13.6万円の積立が必要
- **年間リターン7%**の場合:毎月約11.1万円の積立が必要
ケース2:配当再投資なし
配当を受け取った分は再投資せず、元本のみで増やしていく場合、リターンは約3.5%(配当利回りのみ)と仮定します。
- 目標元本計算:配当利回り3.5%で月10万円の配当を得るには、年間120万円 ÷ 0.035 = 約3,430万円が必要
- 積立額シミュレーション:配当再投資なし、リターン3.5%と仮定します。
- 毎月約16.2万円の積立が必要
やはり複利の効果は大きいですね。配当を再投資するケースとしないケースで毎月3−5万円の積立額に差が生じます。
楽天SCHDに、毎月10万円の積立投資をするシミュレーション
では、積立額を毎月10万円としたとき、65歳時点でどれだけの配当収入が見込めるか、シミュレーションしてみます。
前提条件
- 積立額:月10万円(年間120万円)
- 積立期間:15年間(50歳から65歳)
- 配当利回り:3.5%(SCHDの平均配当利回りを参考)
- 年間リターン(株価成長を含む):
- 配当再投資あり:年5~7%
- 配当再投資なし:年3.5%(配当のみのリターン)
- 計算方法:積立金額に対し複利運用を考慮
ケース1:配当再投資あり
配当再投資を行い、年5%と7%のリターンが得られると仮定して、65歳時点での配当受取額を見積もります。
- 65歳時点の運用元本:
- 年5%リターンの場合:約3,103万円
- 年7%リターンの場合:約3,674万円
- 年間配当額(3.5%配当利回りに基づく):
- 年5%リターンの場合:3,103万円 × 0.035 = 約108.6万円
- 年7%リターンの場合:3,674万円 × 0.035 = 約128.6万円
ケース2:配当再投資なし
配当を再投資せず、元本のみで運用した場合、リターンは配当利回り3.5%と仮定します。
- 65歳時点の運用元本:約2,722万円
- 月10万円を15年間積み立てた合計(1,800万円)に3.5%の単利効果を加味した元本です。
- 年間配当額(3.5%配当利回りに基づく):
- 2,722万円 × 0.035 = 約95.3万円
結果比較
| ケース | 65歳時点の運用元本 | 配当月額 |
|---|---|---|
| 配当再投資あり(年5%) | 約3,103万円 | 約9万円 |
| 配当再投資あり(年7%) | 約3,674万円 | 約11万円 |
| 配当再投資なし | 約2,722万円 | 約8万円 |
- 配当再投資あり:
- メリット:複利効果により65歳以降の受取額が増加する。
- デメリット:積立期間中は配当を受け取らず、リターンを享受できるのは65歳以降。
- 配当再投資なし:
- メリット:積立期間中の配当をすぐに活用できるため、柔軟な資金計画が可能。
- デメリット:65歳時点での年間配当額が少なくなる可能性がある。
どちらが適切かは、積立期間中に配当収入が必要か、もしくは老後資金を優先したいかに依存します。再投資ありの方が長期的には資産が増えやすいですが、積立期間中のキャッシュフローの確保を考えるなら、再投資なしの選択肢も現実的です。
楽天SCHDで毎月10万円積立投資をしたら、配当は毎年どれくらいもらえる?
配当を再投資せずに50歳から65歳の15年間、SCHDに月10万円(年間120万円)を積み立てた場合、毎年得られる配当額を計算してみましょう。
前提条件
- 積立額:月10万円(年間120万円)
- 配当利回り:3.5%(配当を毎年受け取る)
- 積立期間:15年間(50歳から65歳まで)
計算方法
配当を再投資しない場合、毎年積み立てた元本に3.5%の配当利回りがつきます。よって、毎年の配当額は以下のように計算されます。
1年目には積立元本が120万円だけですが、翌年からは累積元本に対して配当がつきます。
年ごとの配当額の計算
以下に、各年末の積立元本とその年の配当額を示します。
| 年数 | 積立元本(累計) | 年間配当額(3.5%) |
|---|---|---|
| 1年目 | 120万円 | 4.2万円 |
| 2年目 | 240万円 | 8.4万円 |
| 3年目 | 360万円 | 12.6万円 |
| 4年目 | 480万円 | 16.8万円 |
| 5年目 | 600万円 | 21.0万円 |
| 6年目 | 720万円 | 25.2万円 |
| 7年目 | 840万円 | 29.4万円 |
| 8年目 | 960万円 | 33.6万円 |
| 9年目 | 1,080万円 | 37.8万円 |
| 10年目 | 1,200万円 | 42.0万円 |
| 11年目 | 1,320万円 | 46.2万円 |
| 12年目 | 1,440万円 | 50.4万円 |
| 13年目 | 1,560万円 | 54.6万円 |
| 14年目 | 1,680万円 | 58.8万円 |
| 15年目 | 1,800万円 | 63.0万円 |
毎年、これくらいの不労収入が得られるのは魅力的ではないでしょうか。最初はちょっといい外食くらい、定年を迎えてからは海外旅行を楽しめそうです。
というわけで、私は、毎月10万円の楽天SCHDへの積立投資を、配当受け取り型で始めます。リタイアするまでの間も、労働ではなく資産から生まれた所得で楽しみたいと思います。